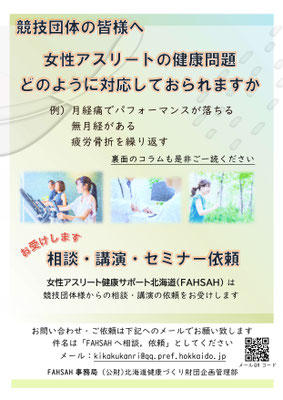第4回 女性アスリート健康サポート北海道セミナー(2023年11月23日)
終了後 伊藤みき講師へのご質問、その他のご質問と回答

伊藤みき 講師へ
ご質問:
「北海道の女性アスリートスポーツの印象をお聞きしたいです。数年札幌に住んで感じたことを。」
回答:
スポーツ、特にウィンタースポーツをする環境が整っていて、札幌は特に、調べるとたくさん女性アスリートをサポートする体制があると思っています。今回のFAHSAHもそうですし、サポートしたい!と思ってくださってる方がいるので、感度高く調べると、いろんなサポートを活用しながら、スポーツを出来る環境があると感じていますし、オリンピックのあった都市なので、そのレガシーがハード面でもソフト面でも残っているな、と感じています。
ご質問:
「ここまでモチベーションを持ち続けている理由が知りたいです。」
回答:
モチベーションがない時もありますが、人間なので浮き沈みを受け入れるようにしています。
ただ、大きな漠然とした人生の目的、みたいなのは家族に共有して、方向性が間違わないようにはしようと思っています。小さな目標は割とその時の状況で、アップデートして、出来ないことも含めて、取り組もうとした中で甲乙つけないようにはしています。出来なかったことに集中すると辛くてモチベーションが下がるので、出来るだけ、前向きになれるような本を読んだり人に会ったり、工夫をするように心がけています。今は、子育てをしているので、その中での反省も多いですが、反省ばかりにならないように、前向きになれるような言葉を発するよう心がけています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
その他のご質問
ご質問:
「練習後に取る補食は、どの栄養素に重点を置けば良いのか。」
回答:
当ホームぺージの「食事・栄養について」のページの 「スポーツと食事・栄養について よくあるご質問」 Q6 をご参照ください。
ご質問:
「ジュニアアスリート 特に月経痛や月経周期に悩む小学校高学年~中学生の低用量ピルの使用にデメリットなどあるでしょうか。」
回答:
欧米では、月経が発来したら(初経以降)であれば、内服を開始してもよいとしている国もあるようですが、LEP製剤(いわゆる低用量ピル)にも含まれるエストロゲンは骨端線(骨の成長する部位)を閉じてしまう(骨の成長を止めてしまう)作用がありますので、日本では身長の伸びが止まってから飲みましょうというのが一般的なようです。
また、LEP製剤では出血量は多くなくても休薬期間に消退出血(月経様出血)を起こすことがほとんどです。エネルギー摂取不足、体重減少、疲労、オーバートレーニング、その他のストレスで本来は月経不順や無月経の体調でも、薬の力で起きる月経があることで体調不良に気づかない、見過ごしてしまうという可能性もありますので注意が必要です。従って、講演の中でも触れられましたが、体重減少や疲労による月経不順、無月経の可能性がある場合には最初からピルを飲むというのではなくまずその原因を改善することから始めましょう。
ご質問:
「学校でジュニアアスリートを支えたいと願う養護教諭ができるサポートは具体的に何があるでしょうか。(ジュニアアスリートに関わらず月経痛で保健室に来室する小学生が多いです)」
回答:
上記のように、身長の伸びの止まっていない小学生などにLEP製剤(いわゆる低用量ピル)を飲んでいただくにはかなり慎重になっていただく必要がありますし、病院を受診して処方してもらわなければならないという面倒もあります。
ここからは回答者(三國)個人の見解になってしまいますが、月経痛があるのは仕方のないこと(その生徒さんが悪いわけではないこと)、他にも月経痛のある人はたくさんいること、月経痛の時は無理をしなくて良いこと(あるいは休んでもいい?でしょうか)、正しい飲み方で痛み止めを飲んで良いこと、などを、ご本人、保護者、そしてほかの先生方、あるいは生徒の皆さんにも広くご理解いただけるようにご周知、ご啓発いただければと思います。いかがでしょうか。
ご質問:
「PMS対策でピルを使用することによって良くなった時のその他の健康のついてはリスクはないのか?」
回答:
ドロスピレノン含有のLEP製剤(いわゆる低用量ピル)は、海外ではPMSやPMDD(月経前不快気分症候群)の治療薬として認可されている国もあるようです。個人個人で薬の合う、合わない、有効、無効の違いもありますが、他のLEP製剤も含めて正しい適応、正しい内服方法で使用していて体調が良いのであれば、もともと薬の持つ薬効・利点、欠点(どんなお薬も利点と欠点[副作用、副反応の可能性]はあります)の他には特別なリスクなどは考えなくても良いでしょう。
ご質問:
「ドーピングが毎年変更になる薬物が気になります。女性は許されて男性が許されない「薬物」(ドーピング)、反対に男性には許されて女性には許されない「薬物」(ドーピング)が知りたい。」
回答:
現時点(2023年)では、女性では子宮内膜症や乳がんなど、男性では前立腺がんに用いられる GnRHアゴニストに分類される薬(ブセレリン、ナファレリン、ゴセレリンなど)は、男性では禁止物質、女性では禁止されないとなっています。ドーピングに関する規定は毎年変更・更新されます。詳しくは、当ホームぺージの「薬・サプリメントについて」のページからもリンクのある日本アンチドーピング機構(JADA)やスポーツファーマシストへご確認ください。
ご質問:
「漢方薬で明らかに「ドーピング」にあたる漢方薬あるいは「生薬」とは?お教えください。」
回答:
講演のなかでも少し触れられていましたが、アスリート(特にドーピング検査のある試合・大会に出場する、あるいは出場する可能性のあるアスリート)の方は、漢方薬は使用しないとお考えいただくのが良いでしょう。
漢方薬は、植物、動物、鉱物などを加工(切る、削る、乾燥させるなど)したもの=生薬を一定の割合で調合し、茹でる、煎じるなどして(あるいは抽出物を顆粒状にして)薬として用いるものです。ドーピング禁止物質を含む生薬として知られているものに、麻黄 (マオウ)、呉茱萸 (ゴシュユ)、細辛 (サイシン)、南天 (ナンテン)、附子 (ブシ)、海狗腎 (カイクジン)、麝香 (ジャコウ)、鹿茸 (ロクジョウ) などがありますが、他の生薬に禁止物質が含まれていない保証はなく、生薬の全ての成分が判明しているものでもありません。またその時々で含まれる成分の濃度が変わっている可能性もあります。
さらに、病院から処方されて治療に使っているとしても、アンチドーピング機構の「治療使用特例」=TUE(Therapeutic Use Exemptions) として認められておらず漢方薬名、生薬名では申請もできません。
市販の薬やサプリメント(風邪薬、胃腸薬、ダイエット用など)の中には、漢方と書かれていなくても漢方薬の処方や漢方薬の成分、生薬を含むものがありますので注意が必要です。
従いまして、繰り返しになりますが、学生さんを含め公式な競技会に出場するアスリートの方は漢方は使わないとお考えいただくのが無難でしょう。
こちらについても、詳しく確認したい方は、日本アンチドーピング機構(JADA)やスポーツファーマシストへご確認ください。
第3回 女性アスリート健康サポート北海道セミナー(2022年11月20日)
終了後 講師の方々へのご質問と回答
ご参加いただいた方々からFAHSAHへのご意見について
矢代直美 講師へ
ご質問:
「現役時代に苦労した点」
回答:
学生時代は自分の実力以上の環境に飛び込んだこともあり、技術的なことも含めチームの練習について行くことに必死でした。
実業団に入ってからは、練習量がかなり増えたことで体のメンテナンスの仕方。また勝敗が重要な環境になり心のリフレッシュの仕方が難しかったです。
どちらも色々と試行錯誤をしながら自分に合う方法を探していました。
ご質問:
「高校時代はあまり聞き取る環境がなかった原因などを、もう少し深く聞きたかったです」
回答:
学生時代に痛みを打ち明けられなかったのは、私の性格に理由があるのかもしれません。
負けずぎらな気持ちが強く、弱音を吐くことで弱い人間と思われるのではないか?休んでいる間に他の子に負けてしまうのではないか?
そんな事を考えていたのかもしれません。
時代や環境の影響で、言い出せない選手もいると思います。また、個人の性格で言葉にできない選手もいると思います。
学生には、苦しみや辛さは言葉にしていいこと。
指導者の方は、アンケートの実施や個別で話を聞いてあげる機会を作ってほしいと感じます。
声に出せない声を聞いてほしいです。信頼できる大人に悩みを打ち明けることの大切さを教えてあげて頂きたいです。
どうぞよろしく願いいたします。
中西麻耶 講師へ
ご質問:
「大きな大会前の心得」
回答:
気
その過程で「これだけやったんだから勝てる」と自信が持てるような練習内容になるように工夫しましょう。
集中については、私の場合は嫌いな時間(集中出来きない時間)と日頃から向き合うようにしました。
例えば私は文字が苦手で本を読むことが嫌いでした。あえて本を読む事にしたのです。
そうするとどうしたら本読みを好きになれるのか工夫するようになります。
そうする事で逃げられない今目の前の出来事と向き合える力が養えます。
この時にどういう状態であれば自分が1番集中出来てるのかも出来れば分析して下さい。
音楽なのか呼吸なのか匂いなのか…それが見つかれば本番の時にそれを身近に持っておく、
または想像する事で集中またはリラックスが出来る状態にしておく事もおススメです。
集中とはずっとしていると疲れてしまうので、ここぞという時に集中出来るようにしましょう。
ご質問:
「勇気をもつ、失敗を恐れずに自分で勇気にチャレンジしていくための心の作り方」
回答:
まずあなたは勇気を持っている事に気付きましょう。
勇気というのは皆さんが生まれながらに平等に持っています。差が出るのは勇気を出すことが出来るか出来ないかなのです。
勇気を日頃から出す習慣を身につけないと大きな勇気は出せません。
なぜかというと、勇気を出すとその勇気を受け取ってくれる人(物)が必ず存在するところにキーポイントがあります。
あなたが頑張って出した勇気を受け止めてくれた人は「感謝」の気持ちや「応援」の気持ちをあなたに返してくれるでしょう。
その気持ちがあなたの中の勇気を育ててくれます。
この作業を繰り返す事で勇気は育ち小さい勇気から大きな勇気を出せるようになります。
どんなトップ選手でも新しい事にチャレンジする時には心臓を握りつぶされたような感じがするし、足だって震えます。
でも大事なのは折角持っているあなたの素敵な勇気を出してあげる事。
あなたが勇気をちゃんと持っている事、どんな人でも恐怖を感じながらでも勇気を頑張って出している事、それに気付いて下さい。
勇気の出し方が分からなければまずは両親のお手伝いをするとかでも良いと思いますよ。
持ちで盛り上げてしまうと気持ちというのは揺らぎやすいので、
練習メニューでしっかりと作って行きます。
ご参加いただいた方々からFAHSAHへのご意見について
現時点(2022年11月末)で回答できるものについて記載させていただきます。
ご意見:
アメリカと国内でのピルの使用や婦人科の相談がどれほど行われているか現状をもっと知りたかった
回答:
欧米のアスリートについては、その調査、報告によってばらつきはありますが、おおむね45%~80%くらいの選手がいわゆる低用量ピルなどで月経対策をしているとされています。日本では、東京2020大会出場女子選手への国立スポーツ科学センターの調査で、オリンピック選手、パラリンピック選手ともに28%の選手が低用量ピルなどで月経対策をしていました。ロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピックではそれぞれ7%、27.4%でした。日本の選手は欧米の選手に比較すると使用頻度は少ないですが、アスリートに限らない一般の人々での使用率は、欧米ではおよそ30-50%ですが、日本では3%程度ですので、生活習慣など様々な要因が関係していると思われます。大事なことは「欧米の選手のようにピルを使いなさい」ということではなく、そういった選択肢も理解したうえで一人一人に最適な方法で対応するということではないでしょうか。
ご意見:
このような講演は指導者の方にしっかり聞いてほしい。各スポーツの関係団体にインフォメーションするべきです。
回答:
私たち、女性アスリート健康サポート北海道(FAHSAH)では、北海道スポーツ協会に加盟するすべての競技団体と中体連、高体連に対して、女子選手の健康問題についての理解を広めるために次のようなチラシを配布して、各団体からの相談受付を始めています。
さらに北海道スポーツ協会が各競技団体からの求めに応じて、合宿会場などでおこなう「スポーツ医科学トータルサポート」に本年度から女性アスリートの健康についてのアンケート聞き取りや講習を加えてもらいました。北海道スポーツ協会のホームページ https://hokkaido-sports.or.jp/kyogi_kyoka_sup/ などをご参照ください。
ご意見:
・月経のことをもう少し掘り下げてお聞きしたい。選手、指導者の立場から具体的にどうしたらいいのかを知りたい。
・栄養士の方のお話も聞いてみたいと思いました。 ・栄養面のことをテーマにして欲しい。
・メンタルケアに特化した講演も聞いてみたいです。
・メンタルトレーニング・ストレッチ(ケガをしにくい体作り)の講演を希望
回答:
ストレッチや身体的トレーニングについては、現在の私たちの体制では対応が難しく、専門家(アスレティックトレーナーなど)にご相談いただくのが良いでしょう。
栄養士の話は、第1回のセミナーでじっししておりますが、月経やそれに伴う症状についての対応や、食事・栄養の話、メンタルケアについては、今後のセミナーで取り上げていけるように検討したいと考えています。
第2回 女性アスリート健康サポート北海道オンラインセミナー(2021年11月23日)
終了後 講師の方々へのご質問と回答
山内 武 講師へ
ご質問:
「記録を出したいアスリートにとって、減量制限やトレーニングの内容を制限されることは、先生のご指摘もあった通り相当の心理負荷と思います。医師として選手の健康管理の点からは制限せざるを得ない場面も多いと思いますが、上手に説得、納得してもらうために留意している点やコツなどありますでしょうか。性別や年齢、競技の内容等でも違いがあるように思いますが、良い方法があればご教示いただけますか。」
回答:
考慮しなければならない点は多いですので、適切な回答は難しいと感じています。今回は女性に限定して、回答いたします。
一番重要なことは各アスリートのバックグラウンドを正確に掴むことだと思います。
1.競技種目(減量の必要が高い種目か?あまり重要でない種目か?)
2.年齢 発育段階によって、対応は異なってくると思います。
トップアスリートの平均年齢も参考になるかもしれません 20歳代中盤、20歳代前半、10歳代後半、10歳代中盤
10歳代中盤がトップになる競技(例えばフィギュアスケート女子など)では、早期引退させることも必要かもしれません(ただこうした競技自体が少し歪んでいるようにも思えます。ルール改正も必要かもしれません)。本来15歳程度の未成熟なアスリートならば、競技よりも健康を優先させる方が適切でしょうが、トップをめざすのならば、健康を犠牲にしなければならない状況は、まずいのではないでしょうか? 一方、 自分自身でリスクをとれる自立した段階のアスリート( 20歳代中盤)では、あえて短期間、健康には少し目をつぶることも必要になってくると思います。
ご質問:
「長距離選手には一時的な軽量化戦略を推奨していましたが、フィギュアスケートのような日々の体重変動が技の感覚に影響を与えるような競技ではどのようなコンディショニングやトレーニングが適しているのでしょうか。」
回答:
フィギュアスケートを専門にコーチングを行ったことがありませんので、適切な回答になるかわかりませんが、考えてみました。氷上トレーニング中心の時期と、一般トレーニングを中心とする時期を分けた方がいいのではないでしょうか。氷上トレーニング中心の時期では、ある程度体を絞って(月経不順にならない程度)、技術を向上させる一般トレーニング中心の時期では、技術トレーニングは維持程度にとどめ、パワー、瞬発力など高めるトレーニング(レジスタンストレーニング*、体幹トレーニング、プライオメトリクス*など)を十分に行います。効果を得るためにはしっかりした栄養が必要です。減量はマイナスです。筋量、筋パワー、アジリティ*の向上をめざします。この時期は月経不順等にはなりにくいでしょう。
(座長注釈: レジスタンストレーニング; 筋に負荷をかけたトレーニングのことで、いわゆる筋力トレなど。 プライオメトリクス; 主に瞬発力を高めるため急激に伸ばした筋肉を爆発的に収縮させるたとえば、連続ジャンプや高いところから飛び降りてすぐにジャンプするなどの運動やトレーニング。 アジリティ; 機敏性、敏捷性とも訳され、状況、刺激、障害に対して素早く反応(停止、動き出し、方向転換など)する能力。 いずれも詳しくはトレーニング専門書などをご参照ください)
山内武、川端絵美 両講師へ
ご質問:
「練習による精神的なストレスは身体的な問題だけではなくパフォーマンスや結果にも影響がありますか。」
回答:
山内武 講師
間違いなくあると思います。精神的なストレスによるバーンアウト等を避けるためには、ピリオダイゼーションを活用してシーズンオフの期間を置くことが大切でしょう。また、心理カウンセラーも活用することも必要でしょう。
川端絵美 講師
私自身の経験から、練習の精神的ストレスについて、練習がつらいなーなどと思うことはありましたが、それが、パフォーマンスや結果に影響があるかは、正直ない気がします。 ただ、天候が悪い日、気分はのらないとか、コースが見ずらいことで消極的な滑りになったりはしました。やる気が落ちる日はありますよね。 また、練習でうまくできないことは、本番でもミスしますから、スキーの斜面など苦手意識をもたないように練習でできるようにしたり、精神的コントロールを意識しましたかね。 緊張を緩和する最大の方法は、絶対的成功率、すなわち練習量しかないと。また、戦闘、集中モードとリラックス、競技ではないと思えるモードの切り替えが必要です。
ご質問:
「セミナーを聴いて無月経などの問題は選手寿命を縮めることはわかりました。選手として競技を続けるのが学生の間のあと2年だとしても、無月経の治療はしたほうがよいのでしょうか。」
回答:
山内武 講師
この件、もう少し背景を知る必要がありそうです。以下の想定で考えてみました。
女子長距離ランナー大学生 20-21歳
ケース1. 10歳代までは、ある程度月経がきており、最近続発性無月経になってきている。
目標の大会まで(本年度)治療を受けず、ベストパフォーマンスを目指す。 大会後、婦人科に行き診療を受け、必要に応じてホルモン療法等を受ける。次年度はベストパフォーマンスを目指すことは少し難しくなりますが、不可能ではありません。 その後、競技から引退する。
ケース2.10歳代から続発性無月経の状態が多い。
まず、婦人科に行き診療を受ける。疲労骨折などが多くみられる場合には、ホルモン療法等を受ける。 この場合には、本年度ベストパフォーマンスを出すことは困難です。次年度はベストパフォーマンスを目指すことは少し難しくなりますが、不可能ではありません。その後、競技から引退する。 また、婦人科に行き診療を受け、なんとか本年度の競技続行が可能なようであれば、ホルモン療法を避け、トレーニングを工夫しながら、ベストパフォーマンスを目指す。大会後、必要に応じてホルモン療法等を受ける。次年度はベストパフォーマンスを目指すことは少し難しくなりますが、不可能ではありません。 その後、競技から引退する。
川端絵美 講師
無月経の治療については、自分にとって重要といちづける大会や練習期間など考慮して、選手をしているから無月経かのか、個人の体質なのかにもよりますが、私としては、時期などを考え、選手としてから将来的なことを考えて治療をしたらよいかと思います。 どのレベルのアスリートかにもよるてはいいますが、頑張ってる方は、オリンピック目指す方も市民大会を目指す方もみなさん自分の目標に邁進されていますよね。なので一概にこのレベルだから治療へ、または競技者として治療は先送りとできませんね。 私の経験では、高校生には、夏などオンシーズン以外の比較的体調管理にむりがないときなどに指導しました。 私自身は、そのような環境ではなかったので対象外にはなりますが、笑い
ご質問:
「オフの期間、練習強度を落とす期間は最低何日必要か。また、その期間を作りたいと監督にどのように伝えたらわかってもらえるでしょうか。」
回答:
山内武 講師
競技種目、年齢により異なると思います。一般的には、一か月はオフをとったほうがいいと思います。 監督さんには、体の不調が予想されることを伝えればいいと思います。あるいは、オフにどうしてもやらなければならない競技以外のことがあることを伝えればいいのではないでしょうか?
川端絵美 講師
スキーならスキーシーズン終わるゴールデンウィークあたりには、軽い練習ですが、それ以降は、休まはほぼありません。1年のイメージだと、8月から11月は雪上トレーニング氷河などに陸上トレーニングも最大限にあるのでかなりハードです。また、1週間のなかで、強弱をつけてました。水曜日、木曜日をピークで週1日は、完全オフ。軽いランニングとストレッチていどなど。 まったく、スキーを感じない方が良いと判断した場合は、そのようなやすみ。 身体はつらいが良い感覚を戻すために、自由に滑りまくるみたいな、両極端なオフをしました。自分の感覚でもありますが、練習の大きな組み立てを1年、マンスリー、週など始めから話し合うと良いのではないでしょうか?
川端 絵美 講師へ
ご質問:
「とても興味深いお話が聞けて良かったです。以前、スポーツ関連の論文を読んだ際、女性アスリートの三主徴について理解しているが改善しようとしない又は出来ていないという女性アスリートが多くいる報告がありました。そこで、実際にアスリートの方を指導されている立場として、アスリートに対して食生活や生活環境などを改善させることの難しさを感じることはありますか?」
回答:
改善させることは、私は可能と考えますが、実業団チームなど常に一緒にいられない、学生、子供は、指導とはなれている家庭での生活など、関わる人全員が何を目的にそのアスリートをサポートするか役割分担を明確にし、必要な知識を持ち進むしかないので、そこが難しいと感じています。
第1回 女性アスリート健康サポート北海道オンラインセミナー(2020年11月27日) 終了後 講師の方々へのご質問と回答
阿部雅司 講師
ご質問:
「とても周囲の方に救われ、支えられてきたように伺えた。ただ、これだけ情報が溢れる現在の世で、昔のように人の言葉だけで信じれなくなっているように思う。どのようにしたら、お互いに信じ合え、尊敬し会える関係になっていくでしょうか。」
回 答:
お互いに尊敬しあえる関係になるためには、まず相手を信じる事が大切だと思います。それと相手の立場になって「何を言ったら喜ぶかな?何をしてあげたら嬉しいかな?」と考えて行動していたら必ず良い関係になると思います。
又、もし人の嫌なところが気になる時には、その人の良い所を探してみてください。嫌なところを指摘するより良いところを褒めるようにして行くと人との関係が良くなると思います!
寺田明日香 講師
寺田明日香講師へいくつかご質問をいただきましたが、担当マネージャーさんから、練習、講演、ご家庭のこと、その他で非常にお忙しく、セミナー後のご質問に回答する余裕がないのでご了承ください と ご連絡をいただきました。
従いまして、 座長を務めました 三國から 寺田講師がご講演の中で話されていたことから 簡単に解説させていただきます。
ご質問:
「貧血の原因は食事量の減少のほかに、偏食などはなかったのですか? 現在、もしも克服できていたら、その方法も教えてください。」
回答・解説:
寺田講師は、一時引退前の体調を崩されていた時、摂食障害傾向にあった時期の他に、もともと月経量が少し多めであったとおっしゃっていたと思います。現在は、ホルモン含有IUD(子宮内装具)を使用されていてほとんど気になることはないとおっしゃっていたと思います。
補足解説: ホルモン含有IUDは、きちんと病院を受診して診療を受けその利点、欠点などを理解したうえで医師に挿入してもらわなければなりません。妊娠、出産の回数や子宮の大きさ他の条件で使えない場合もあります。いわゆる低用量・超低用量ピルやプロゲスチン製剤といった内服薬についても医師の診断、処方のもとに使用しなければなりませんので、産婦人科を受診しご相談ください
ご質問:
「メンタルが弱くなった時、精神的に辛い時どのように改善していましたか。その時体調にも変化がありましたか?」
回答・解説:
ご講演の中では、「精神的につらい時、あるいは肉体的にコンディションが悪い時は、 今はそういう時期であると自覚して、理解して、その時にできる(できる範囲で)ベストを尽くそうとかんがえる」とおっしゃっていたと思います。
阿部講師、寺田講師 お二人へ
ご質問:
「息抜きや楽しみとして、お菓子類はどのような種類のものをどの程度食べることをよしとしているでしょうか」
セミナー時にも講演させていただいた 公認スポーツ栄養士 蜂谷愛 より 回答・解説させていただきます
回答・解説:
1日の必要栄養量内におさまっていれば特別避けなければならないものはありません。
一般にはおやつ(間食)は主に「こころ」を満足させるためのもので,エネルギー量の目安は1日200kcal程度とされています。お菓子の栄養素では炭水化物と脂質をポイントに栄養表示を確認してみましょう。揚げていない和菓子(せんべい,饅頭など)は炭水化物中心,スナック菓子やチョコレート,クッキーなどは炭水化物と脂質が多くカロリーも高くなります。その日の食事の脂質が多めであればお菓子は脂質の少ない物を選ぶなどして調節すると1日の栄養バランスをとりやすくなります。
おやつはアスリートや子どもにとっては食事で足りない栄養補給ができる大事な時間でもあります。食事で不足する栄養素を補う目的でとることを補食といいます。ビタミンもとれる果物,カルシウムが豊富なヨーグルトでとるといったほかに,サンドイッチなど主食と主菜が補えるものを利用することもあります。アスリートの場合,練習前なら糖質中心,練習後なら糖質・たんぱく質のとれる補食がよいでしょう。
※補食については,詳しくは当ホームページ「食事・栄養について」のQ4をご参考ください。
ご質問:
「人間生活においてスポーツとは何でしょうか?」
というご質問をいただきました。 大きなテーマのご質問であり、講師の方々からの回答はございませんでした。 回答とはなりませんが、女性アスリート健康サポート北海道(FAHSAH)といたしましても、スポーツの持つ意味、意義についても考えながら活動してまいりたいと思います。